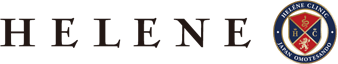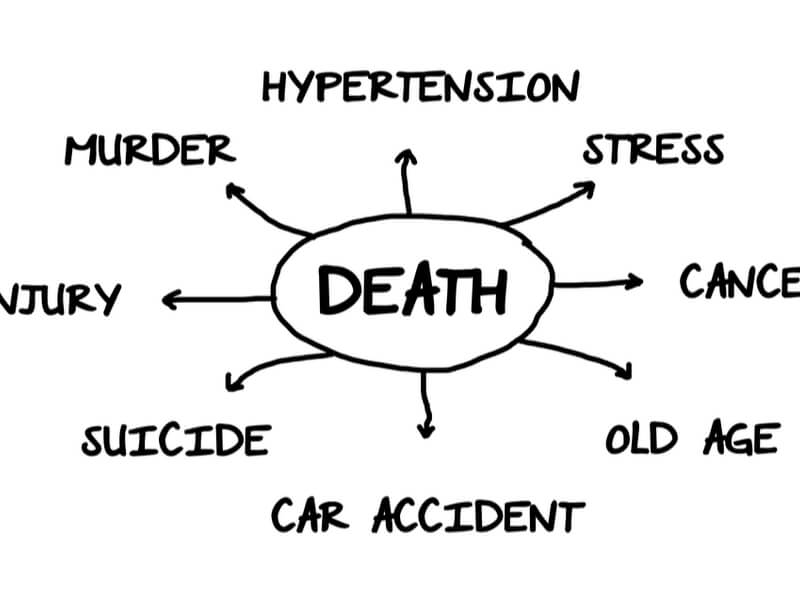
近年、日本では高齢者の死亡原因に変化がみられるようになりました。
かつては少なかった老衰死の割合が高くなり、その背景としては超高齢化社会や医療科学の発展などが考えられています。
本記事では厚生労働省が行っている人口動態調査の結果をもとに、高齢者の死因とその推移についてご紹介します。
目次
高齢者の死因と推移
高齢者の死因を年齢別にみていきましょう。
55~79歳までの死因は悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、自殺、不慮の事故の順に多く、この間順位に変動は見られません。
しかし、65歳以上になると肺炎が増え始めるのが肺炎です。80歳以上になると脳血管疾患と順位が入れ替わり、肺炎は第3位となります。
そして、85歳頃になると、不慮の事故に代わり老衰が増え始めます。老衰の死亡率は年齢が高くなるほど上昇し、95歳以上になると第1位まで順位が上がります。
高齢者における死因の詳細は、以下をご覧ください。
悪性新生物(癌)
悪性新生物は高齢者の死因の中で最も多く、日本人の3〜4人に1人が悪性新生物で亡っています。
年齢別に見ても多くの年代で第1位の悪性新生物ですが、発症の原因は遺伝子異常の積み重ねです。
遺伝子異常は年齢を重ねるほど起きやすく、団塊の世代が80代後半になる2030~2035年くらいまでは悪性新生物による死亡者数は増え続けるといわれています。
しかし、死亡率は1990代半ばをピークに減少しており、癌の生存率は多くの部位で上昇傾向にあります。
心疾患
50歳以降から第2位以上を維持し続ける心疾患には、高血圧性を除く心臓の病気全般が含まれています。
その大部分が虚血性心疾患で、狭心症や心筋梗塞といった心臓の筋肉が酸素や栄養不足を引き起こす病気です。
心疾患による死亡率は1994年頃一時的に減少しましたが、1997年からは再び上昇傾向となっています。心疾患の主な原因は動脈硬化だといわれており、その動脈硬化は遺伝や加齢のほか、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病が密接に関係しています。
心疾患の罹患者率は高齢になればなるほど高くなることが知られており、死亡率の上昇は高齢化が影響していると考えられています。
老衰
老衰とは加齢によって生命維持にかかわる脳や肺、心臓などの臓器機能が低下し、衰弱して亡くなることです。
老衰の多くは平均寿命である80歳をボーダーとしており、病気や事故などの死因が当てはまらない自然死だと認められる場合に該当します。
85歳から診断されることが多くなる老衰は、95歳以上になると死因の第1位となります。
もともと死因として少なかった老衰ですが、高齢化や医療科学の進歩により珍しいことではなくなりました。実際、老衰による死亡者数は10年前と比較して、約3倍にも増加しています。
脳血管疾患
脳血管疾患は脳血管が詰まる、敗れることが原因で起こった脳・神経の病気全般のことをいいます。
かつて脳血管疾患は死亡率第1位でしたが、現在は55歳~79歳までは第3位、80歳以降では第4位に落ち着きました。脳血管疾患が減少した理由としては、医療技術の進歩や高血圧・糖尿病・不整脈の予防医療の推進などが考えられています。
肺炎
肺炎は65~79歳で第4位、80~100歳以上になると第3位に順位が上がります。
戦後、抗菌薬の登場によって死亡率が劇的に減少した肺炎ですが、1970年頃から再び増加傾向となりました。
しかし、過去と現在では死亡年齢に大きな変化がみられます。
かつて肺炎による死亡者は乳幼児と高齢者の二峰性でしたが、現在は65歳以上の高齢者がほとんどです。現代で肺炎の死亡者が増え続いている理由は、日本の高齢化が関係しているといえるでしょう。
不慮の事故
どの年代でも死因の上位にランクインしている不慮の事故ですが、85歳を過ぎると徐々に減少していきます。
85歳は同時に老衰による死亡率が上昇してくる時期でもあり、不慮の事故による死亡率の減少は生活環境の変化が関係していると予測されます。
不慮の事故に遭うような外出はしなくなり、家の中に引きこもりがちになっていく高齢者の姿が反映されているようです。
高齢者の死因まとめ
本記事では、高齢者の死因ついてご紹介しました。
・高齢化や医療科学の進歩により高齢者の死因が変化した
・生活習慣病に起因する病気の死亡率が上昇している
・高齢者の死因の第1位は悪性新生物で、現在も上昇傾向にある
・心疾患による死亡率は一時的に減少したが、現在は上昇している
・高齢化が進み老衰が多くみられるようになった
・かつて死亡率第1位の脳血管疾患は減少傾向にある
・肺炎による死亡率は戦後に減少したが、高齢化によって再び上昇している
・不慮の事故は老衰が増える85歳頃から減少する
高齢化による老衰死や生活習慣病に起因する病気の増加は、いずれも時代背景が大きく関係しています。
2040年まで続くといわれる高齢化社会。今後はどのような変化をみせるのでしょうか。
監修:医師 津田康史